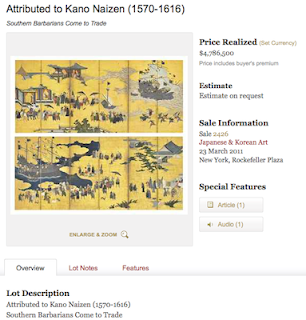ハーモニウム(Harmonium)
水星でこれまでに発見された、ただひとつの生物だ。ハーモニウムは、ほら穴に住んでいるんだよ。これよりも美しい生物はちょっと想像できない。
(『いろいろなふしぎと、なにをすればよいかの子ども百科』)
これまで色々な物語の中で生まれてきた空想上の生き物。。。
そのなかでいちばん美しく素敵な存在は、この本のなかに。
『タイタンの妖女』
カート・ヴォネガット・ジュニア(1959)
SF小説で世界観に入りこむまで読み進めにくいけれど、全て読み終わるとおとぎ話を読んだような感覚になる。不思議。むかしからあるような神話みたいで、完璧で残酷な物語。
話の中で主人公が水星に彷徨い着いたとき出会うのが、ハーモニウムという謎の生き物たち。性は一つしかないし、感覚は触覚しかない。
彼らは弱いテレパシー能力を持っているけれど、送信し受信できるメッセージはたった二つだけ。
"here I am(ボクハココニイル)"
"so glad you are(キミガソコニイテヨカッタ)"
。。。たったこんな言葉が、じじじじーんと胸を打つ。
その感動を味わって以来、ずっと心に残っている言葉。こんな見事なコミュニケーションあるかな。そんなことで、わたしのブログタイトルもここから付けてみたりしたのです。
この生き物は、小さな菱形で半透明になっている。水星の洞窟の壁からは黄色い光がでているが、その透明体を通り抜けるとき、光はアクアマリンの色に変わる。何の意味もないけど、その色と形をつかって、壁の上で整列し模様をつくって遊ぶ。水星がうたう歌を食べて生きている・・・そしてその音楽好きなところと、美への奉仕のために熱心に形づくろうとするところから、地球人たちがハーモニウムという美しい名前を与えたという。そんな素敵な生き物。
あたりまえだけども
やっぱり物語は物語で
音楽は音楽で
絵画は絵画で
それ以外では表せないものが凝縮している。
どれだけここでハーモニウムを説明しても、物語の中でこそじゃなきゃ味わえない感動がある。その興奮を人はどうしても伝えたいから言葉で表そうとするけど、言葉とはなんてはがゆくて不完全なツールなんだろう。だからハーモニウムに憧れるんだけども。
作者がこの生命体を思いついたときにはどんなイメージが巡って、どんな感動があったかな。全然考え及ばない。でもハーモニウムまでの美しい想像はできなくても、その端くれは誰の日々のなかにもちりばめられてるんじゃないかな。
..それはふと目を落としたコーヒーカップの中に ?
..それともレンズを通せば見える光の流れの中に ?
いつか想像のかたまりになるといいな